今回は肩の腱板(けんばん)を損傷して10年ほどが経過する筆者の実際の状況や体験談を通して、肩の腱板(けんばん)を損傷した後に、競技レベルのベンチプレスは行えるのかを解説していきたいと思います。
実際の研究データなども用いて解説検証していきますので、肩の腱板(けんばん)損傷に悩む競技者の方は是非一読して頂けると幸いです。
少し長いですが、どこよりも細かく肩の腱板損傷について記事を書いていきますので、本気で悩んでいる人は是非最後までお付き合い下さいませ。

読むのに時間はかかると思いますが、きっと参考になる内容になっているはずです!
肩の腱板(けんばん)損傷とは
肩の腱板(けんばん)損傷とは、肩関節を構成する「腱板」を形成する4つの筋腱(棘上筋・棘下筋・小円筋・肩甲下筋)のうち、いずれかの腱が炎症を起こしたり、部分的または完全に断裂してしまった状態を指します。以下のポイントで整理します。
1. 腱板の役割と構造
- 役割:肩関節(上腕骨と肩甲骨からなる球関節)を安定させ、腕を挙げたり回したりする際に上腕骨頭を適切な位置に保つ。
- 構成筋腱:
- 棘上筋(きょくじょうきん)腱
- 棘下筋(きょくかきん)腱
- 小円筋(しょうえんきん)腱
- 肩甲下筋(けんこうかきん)腱
2. 損傷の主な種類
- 腱炎(けんえん)・腱板周囲炎
- 繰り返しの動作や加齢によって腱がすり減り、炎症を起こした状態。
- 部分断裂(パーシャルティア)
- 腱の一部が切れてしまった状態。痛みは強いものの、腕を動かせることが多い。
- 完全断裂(フルスレットティア)
- 腱が肩骨から完全にはがれ、腱の連続性が失われた状態。腕を一定以上動かせなくなることもある。
3. 主な原因
- 加齢・退行性変化:40~60代以降で発症頻度が上昇
- オーバーユース(使い過ぎ):スポーツ(野球、バレーボール、テニスなど)や職業的動作
- 外傷:転倒・ぶつかりなどの大きな衝撃
- 肩峰下インピンジメント:肩甲骨の骨性構造が腱を圧迫
4. 代表的な症状
- 夜間痛:横向きで寝ると強く痛む
- 挙上制限:腕を水平以上に上げにくい
- 外旋制限:肘を90°に曲げた状態で手のひらを後ろに回しにくい
- 力が入らない:力を入れて腕を上げようとしてもふらつく
5. 診断と治療の流れ
- 問診・理学所見(Jobeテスト、ドロップアームテストなど)
- 画像検査:超音波(エコー)、MRIで断裂の有無・程度を評価
- 保存療法:安静、NSAIDs(消炎鎮痛薬)、理学療法(ストレッチ/筋力強化)
- 注射治療:ステロイド注射やヒアルロン酸注射
- 手術療法:断裂が重度・慢性化し保存療法で改善しない場合、関節鏡下縫合術などを検討
まとめ
肩の腱板損傷は、腱板を構成する腱に炎症や断裂が生じ、肩の可動域制限や夜間痛を引き起こす代表的な疾患です。症状や断裂の程度に応じて、まずは保存療法で経過をみることが多く、改善が得られない場合には手術が選択されます。
軽度の場合は早期に適切な診断とリハビリを行うことで、日常生活への影響を最小限に抑えることが可能です。
逆に重症の場合は自然治癒やリハビリなどでの改善はできず、消炎鎮痛などで散らしながら我慢するか、手術するしか選択肢がなくなってしまいます。

ここからは筆者の状況を事細かに説明します。
参考にしてみてください。
筆者の肩の腱板(けんばん)損傷の状態と経緯
筆者のトレーニング歴

筆者は17歳でトレーニングにのめりこみ、当記事執筆時点の38歳まで長年ナチュラルボディビルに打ち込んできました(途中情熱を失って3年くらいほぼ自重トレのみの空白の期間があります…笑)。
トレーニング10年目くらいまではベンチプレス、スクワット、デッドリフトを中心に、BIG3信者として日々先輩ビルダーにしごかれて頑張っていたのですが、肩と腰を痛めてしまい、そこからはマシン特化トレーニーとして筋肥大を追求してきました。


↑特に大胸筋の強さにはSNSでも定評があり、一時期はナチュラルチェストモンスターなどと呼んで頂いたり、パーソナルの依頼なども多数頂いたりと、自他ともに認める大胸筋の鬼としてマシントレーニングを満喫していました。
▶大胸筋育成塾 | ナチュラルボディビル研究所
∟筆者監修の完全無料の大胸筋育成コンテンツ
筆者の競技への取り組み状況


↑筆者は2019年にMDCバーベルクラブというトレーニングチームを立ち上げ、多くのトレーニング愛好家、競技者が在籍しています。
元々は筆者を含めナチュラルボディビル、フィジーク、格闘技を嗜むメンバーが9割で構成されていたMDCバーベルクラブだったのですが、2023年に転機が訪れました。
パワーリフティングの実力者が加入した事と、ボディビルおよびフィジーク界のドーピング汚染問題に嫌気がさしたメンバーたちの多くがパワーリフティングに転向した事などが重なり、パワリフ色がかなり強いチームに変化していったのです。
大きな大会などで優勝するメンバーも増えてきたり、チームのグループLINEがパワリフトークで溢れかえったり…。
なによりパワーリフティングという競技と真っ直ぐに向き合うメンバーたちを見ていたら、肩と腰を痛めるまではベンチプレスが大好きだった筆者もたまらなくなってしまい、この記事を執筆している2025年、約10年のブランクを経てベンチプレスの競技に復帰する事になったのです。

メンバーからの刺激が強すぎて第一線を退いて長かったのですが、妻の心配をよそに競技への復帰をする事に…。
長年の無茶なトレーニング生活でもうボロボロのおっさんですが、果たしてどこまでやれることやら…(笑)

競技系のトレーニング再開直後に痛み

↑多数の優勝経験を持つ女性パワーリフターのメンバーにベンチプレスを見てもらいながら、大会に向けて約10年ぶりにベンチプレスの練習を再開した筆者でしたが、練習再開初日からすぐに肩の痛みはやってきました。
10年もトレーニングのプログラムからベンチプレスを外していたので「もしかして良くなってて痛みは出ないんじゃないかな…」なんて甘い事を考えていたのですが、やっぱり再開した途端に激しい左肩の痛みが出てしまいました…。
なんだかんだでベンチプレスをやめてからもマシントレーニングの記録は伸びていましたし、痛い位置に入らないインクラインチェストプレスに関しては200kg近く挙げれていたので、「ベンチプレスも150kgくらいならいけるんじゃないかな…」とか考えていたのです…。でも本当に愚かでしたね…。
長らくベンチプレスをしっかりやってなかったので忘れていたのですが、この腱板損傷は痛いだけじゃなくて、力が入らないんです。

ベンチプレスを完全に舐めていました…。
というか腱板損傷を侮ってました…。
筆者の痛みの症状

筆者の場合は筋肉でしっかりコントロールできて、なおかつ肘が胸よりも後ろに降りない位置までのエクササイズならば、腱板損傷の痛みはそこまで酷くは出ないのです。
もちろん無痛ではないですし、マシントレーニングだとしても無理をして筋肉でのコントロールを一瞬でも失うと激痛が走り、その後数日~数週間ほどは痛みが出たりはありました。
しかしベンチプレスでの痛みはやはりレベルが違いました。
競技の練習再開3か月で練習がまともにできないレベルで左肩が痛くなってしまい、朝起きて寝るまで常に痛みが出ているような状態にまで悪化してしまいました。
そしてついには痛めていなかった右肩まで同じような痛みが出てしまう状態にまで陥ってしまい、大会出場時にはまともにウォーミングアップすらできないレベルで両肩が痛む状態に…。
そんな中ベンチプレス大会での※3試技目、2試技目まで同じ重さを挙げていたライバルに勝つため、練習では成功した事がない重さに挑戦する事にしたのです。
※ベンチプレスの大会では3回の試技でのMAX重量を競います。
試合が始まる前に痛み止め(もちろんドーピングに違反しない認可された痛み止め)を飲みましたが、まるで効かずにズキズキと肩が痛む状態のまま、いつもは挙がらない重さでしたがなんとか大会パワーで挙げきる事に成功しました。
しかしその無理がたたり、大会終了後はもう今までにないくらいの肩の痛みが残ってしまいました。

しかも結局3位は私ともう一人競っていた人が同記録で2人いて、最終的に体重が彼の方が軽かったため体重比で私は4位という残念な結果に…(´;ω;`)
無理をして肩をさらに痛めたというのに…トホホ…。
そして大会でのダメージが決定打となり、もはやベンチプレスの練習どころか二頭筋のトレーニングも背中のトレーニングもまともにできない状態になってしまい、これはさすがにまずいと感じ久しぶりに整形外科を受診する事にしたのです。
整形外科での診断と処置
絶望的な診断結果
チームのメンバーの紹介でスポーツに知見のある整形外科を受診しました。
親身になって症状や競技の相談に乗ってくれて、「なんて素敵なドクターなんだ…」と感激していたのですが、検査やレントゲンの結果を見ながらドクターから衝撃のセリフが飛び出しました…。
「残酷かもしれないけど、競技を引退するか、手術に懸けるかしかないね…。」

いやああああああああああ~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!聞きたくなかったあああああああああ
はい…。というわけで10年休んだところでやはり肩の腱板損傷が治っているわけもなく、さらに再開したベンチプレスの練習により筆者の左肩はもう限界を迎えていました…。
ただ同じくらい痛くなっていた右肩は腱板損傷などはしておらず、恐らく左肩をかばって無理をさせ続けた事と大会で無理をした事による一時的な炎症だろうという事です。

うーーん…、左肩は残念だったけど右肩は無事か…、これは複雑な気分…。
手術をした場合の競技復帰率がエグい…
ちなみに肩の腱板損傷の手術には2種類ほど方法があるそうで、どちらを選択したとしても術部の周辺組織や筋肉への影響、後遺症による影響を考えると、競技への復帰はかなり難しいとの事…。
これは実は整形外科に行く前から知っていた事で、肩の腱板損傷に詳しい知人も手術したら日常生活は改善するだろうが元の競技レベルには恐らく戻れないと言っていましたし、自身で色々と調べた時にも厳しい事がたくさん書いてありました。
とある研究によると、2010年から2016年にMLBの選手151名が受けた腱板手術について分析した結果、以下のような悲しい結果がでたようなのです。
| 手術名 | RTS率(競技復帰率) |
|---|---|
| デブリードマン(腱板部分切除術) | 50.8% |
| 腱板修復術 | 33.3% |
なんと約半数以上の選手が競技への復帰はできなかったんです。
しかも復帰できた選手もパフォーマンスが低下したり、成績向上が見られなかったり、痛みが軽減するに留まったりと、理想的な結果とはいえない現実が待っていたそうです。
要するに肩の腱板損傷を悪化させてしまった場合、ドクターの言う通り競技をやめるか、復帰の可能性は低いが手術に懸けるしかなく、復帰できたとしても以前のパフォーマンスは取り戻すのは限りなく難しいという事。

いやあ…。これは痛くても我慢してやる方が筆者としては良いような気がするなあ…。
様々な手術経験者の体験談をリサーチ
あくまでも上記のデータはMLB選手の一部を対象にした限定的なデータですので、筆者なりに他の競技者の手術体験者や、一般の肩の手術体験談をじっくりと調べてみました。
幸運な事に令和7年のいまは超ネット社会であり、国民総SNS時代とも言われる時代です。
以前ならブログ記事や病院や研究機関の発表したデータくらいしか見れなかったわけですが、今はYouTubeなどにいくらでも腱板損傷の手術体験談が投稿されていました。
おかげで体験談の収集には事欠きませんでした。

でもそのリサーチ結果は想像以上に残酷でしたああああああああああああああ(´;ω;`)
そう、MLB選手の術後データよりももっと残酷なリサーチ結果がでちゃいました…。
競技への復帰どころか、日常生活に戻る事ですらかなりの時間を要するようで、なんとある体験談をYouTubeに投稿していた人によると、スポーツの許可がおりたのは手術から約6ヵ月後だったそうです…(しかも軽度の運動)。
それどころか術後はしばらくの間は肩に装具がつけられ、運動はおろか動かす事すらできないそうなんです。その期間なんと7週間から3ヵ月(症状の程度による)。
もちろんそんな長い期間肩を固定されていると肩の筋肉はおろか腕の筋肉も激減し、自分の腕ですら重たく感じてしまうほどなんだとか…。
筆者も以前とある手術と入院で2ヶ月ほど運動が出来ない時期があったのですが、信じられないほどに筋肉や神経が衰えてしまった事がありました。
たった2ヵ月であのレベルのパワーダウンだったのに、6ヵ月もだなんて多分正気を保っていられないと思います…。

2ヶ月筋トレできないくらいそんなにヤバイか?と思った方もいるかと思いますが、
2ヵ月筋トレしないのと、2ヵ月まるで動かせないのとでは筋肉の衰え方は別次元なんです。
2ヶ月筋トレせずに普通に暮らしているならばまだしも、2ヶ月まるで動かせないとなると、本当に信じられないくらいに衰えます。
下手すると取り戻すのに1年以上かかります。
筆者が選択したのはこれ

結局筆者が選択したのは、痛み止めの注射を打ってごまかしながら競技を続けるという選択肢です。
強力な鎮痛抗炎症効果があるステロイド注射を両肩に打ち、練習できる程度に痛みを軽減させながらベンチプレスの練習を続けるという道を選びました。

ちなみにこの痛み止めのステロイド注射がまた曲者なんですよ…。
もちろんナチュラルの敵であるアナボリックステロイドとは全くの別物なのでご安心くださいね!
この痛み止めのステロイド注射はアナボリックステロイドとはむしろ真逆の効果を筋肉に与えるらしく、なんと打った周辺組織、筋肉、皮膚などを弱体化させ、脆くするというのです…。
たんぱく質分解作用があるらしく、要するに打った場所のパワーダウンを引き起こす可能性があると言うのです。
これは今までメタボリックよりもカタボリックを恐れて生きてきたボディビル思考の筆者にとっては、かなり深刻な副作用ですし、簡単には打つ決断は下せませんでした…。
ナチュラルトレーニーにとって筋肉が分解される注射なんて、ハラキリ切腹レベルで衝撃的な事ですからね…。
でも痛くて練習ができないんじゃ今後の大会での成績は期待できませんし、納得のいく結果が出せるまではしっかりやり抜きたいので、苦渋の決断でしたが、両肩にこの悪魔のたんぱく分解ステロイド注射を打つ事に決めたのです…。
かかった費用
ちなみにこの日は、初診料、診察代、注射2本、レントゲン結果のCD-ROM化代、全部合わせてなんとたったの5500円でした。
正直数万円を覚悟していたのでびっくりしましたが、めちゃくちゃ良心的でリーズナブルなお会計に、「え?これなんか間違ってませんか?注射2本分料金入ってますか?」と事務の方に聞いてしまうほどでした(笑)

もちろん病院によりけりだとは思うので、参考までに。
処置後の肩の状況

ステロイド注射後の両肩の状況としては、腱板損傷の左肩はかなり痛みが落ち着きましたが、一時的な炎症のみと言われた右肩はなぜか痛みが良くも悪くもならず平行線のままです。
ドクターいわく、たぶん左肩はステロイド注射してもあまり効果はないかもしれないけど、右肩はおそらくかなり良くなるだろうとの事でしたので、筆者もまあそうだろうな…と思ってダメもとで打ったのですが、なぜかあまり効かないだろうと思っていた左肩が良くなり、軽症だったはずの右肩は痛いままなのです。
トレーニングで言うと、左はワンハンドのチェストプレスだと100kgでも痛みはでませんでした。
しかし右は20kgでも痛くてダメでした…。

な…なぜだ…(笑)
痛み以外の所でいうと、懸念していたステロイド注射によるパワーダウンは今のところ感じられませんが、どうなんでしょうね…。
ちなみに注射後2日間は注射による痛みでトレーニングはおろか、日常生活での重たい物を持ち上げる動作もきつかったです。
コロナの予防注射のそれに少し似たけだるさと痛みを感じました。
それに関しては3日目にはほとんどなくなってました。
稀に感染症などを起こす場合もあるとか言っていたので、まあステロイド注射後の数日間は安静にしておいた方が無難でしょう。
あ、それからこの痛み止めのステロイドは、多用すると深刻な組織崩壊や、皮膚、筋肉、骨の弱体化を招く恐れがあるため、一度打ったら最低3ヵ月は空けろとドクターが仰ってました。
さらに競技によっては競技時の使用が禁止されておりドーピング違反となる恐れがあるため、競技時以外の使用をする事(パワーダウンするのにNGなのか…)。
肩の腱板損傷まとめ
というわけで今回は筆者の体験やデータを基に肩の腱板損傷とアスリートの葛藤について記事を書いてみましたがいかがだったでしょうか。
肩の腱板損傷についての簡易的なまとめは以下の通りです。
・軽度ならリハビリで改善する可能性も
・重症の場合は基本的に手術しか治療法はない
・手術による影響で競技に復帰できる可能性はかなり低い
・運よく復帰できても手術前のパフォーマンスを取り戻せる可能性は引くい
・ステロイド注射は筆者のように効く場合もあるが、効かない場合も多い
・このステロイド注射はアナボリックステロイドとはまるで異なるもので、むしろ筋肉の分解作用があるため、パワーダウンの可能性あり
・パワーダウンの可能性はあるが競技時の使用はドーピング違反となる可能性が高いため、競技時には使用しないこと
・一度打ったら最低3ヵ月は空ける事
・要するに競技者、アスリートは肩の腱板を損傷すると絶望的…(´;ω;`)
ではではご閲覧ありがとうございました。
もしもこの記事が役に立った!と感じて頂けましたら、シェア&ブックマークして頂けましたら幸いですm(__)m
▼虚弱体質ビルダーである筆者の関連記事▼▼
ある日突然、急性帯状潜在性網膜外層症/AZOOR(アズール)になりました…。 | ナチュラルボディビル研究所 by.けんた店長
【地獄の痛み】37歳で手足口病にかかりました…|症状の経過とオススメの対症療法を解説《発症2日目からの地獄》 | ナチュラルボディビル研究所 by.けんた店長


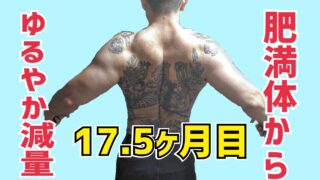




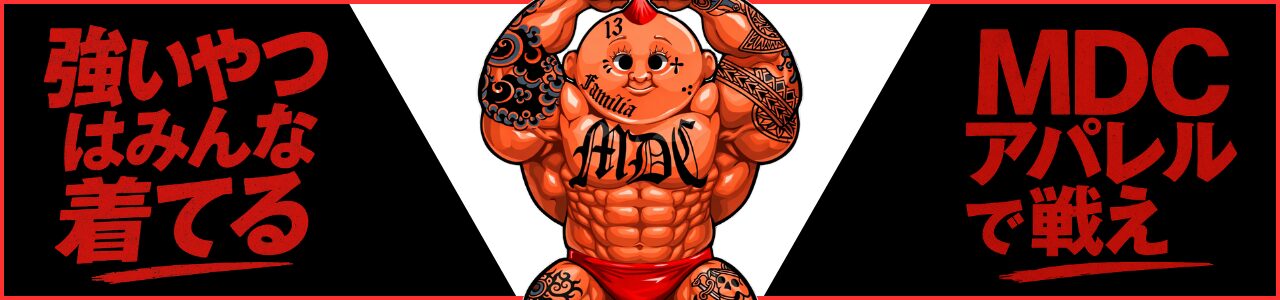





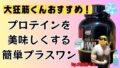




コメント